相続トラブルを防ぐ切り札!家族信託の仕組みと使いこなし術、意外な落とし穴まで一挙公開
家族信託とは何か?
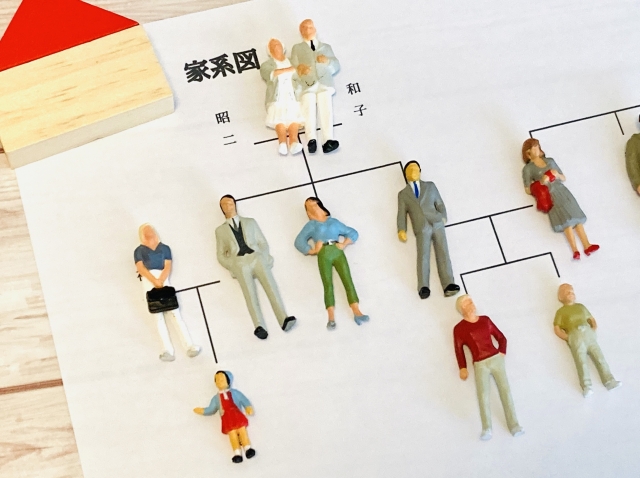
家族信託(民事信託)とは、自分(委託者)の財産の管理・処分権限を信頼できる家族など(受託者)に託し、その財産から生じる利益を家族(受益者)が受け取れるようにする仕組みです。委託者・受託者・受益者の三者間で「信託契約」を結ぶことで成立し、契約内容に沿って受託者が財産を管理・運用します。例えば親が所有する不動産や預貯金を子に託し、親自身や家族を受益者とすることで、生前から財産管理を任せつつ、将来の資産承継もスムーズに行えます。契約で自由に条件を定められるため、各家庭の事情に合わせ柔軟に設計できるのも特徴です。
家族信託でできることとメリット
家族信託を活用すると、生前から財産管理と承継方法を一貫して決めておけるため、さまざまなメリットがあります。代表的なものを挙げます。
認知症による資産凍結の防止
将来、親が認知症になっても、事前に信託契約を結んで子を受託者としておけば、銀行口座から生活費や医療費を引き出したり、不動産を売却して介護費用に充てたりすることが可能です。成年後見制度利用時の口座凍結を避けつつ、柔軟で迅速な財産管理が行えます。
不動産の円滑な管理・承継
収益不動産をお持ちの場合、家族信託により親が子に管理を任せることで、親が万一判断能力を失っても賃貸契約の継続や資産の凍結回避が可能です。また、信託契約に遺言の機能を持たせておけば、親の死亡後に財産の帰属先を指定でき、孫の代まで含めた承継も設計できます。遺言書ではできない二次相続以降の承継先指定も可能で、一族の資産を長期的・計画的に引き継げる点も大きな利点です。
遺産分割トラブルの予防
家族信託によって「誰にどの財産を継がせるか」を生前に確定できるため、相続人同士の争いを減らす効果が期待できます。特に複数の相続人で不動産を共有名義にすることで起こりがちな揉め事も、信託を使えば回避できます。遺産分割協議の手間も省け、遺族の精神的・事務的負担を軽減することにもつながります。
遺言・成年後見制度との違い
家族信託は、遺言や成年後見制度と目的や機能の一部が重なる反面、それぞれ異なる特徴を持ちます。上手に使い分けるため、主な違いを押さえておきましょう。
遺言との違い
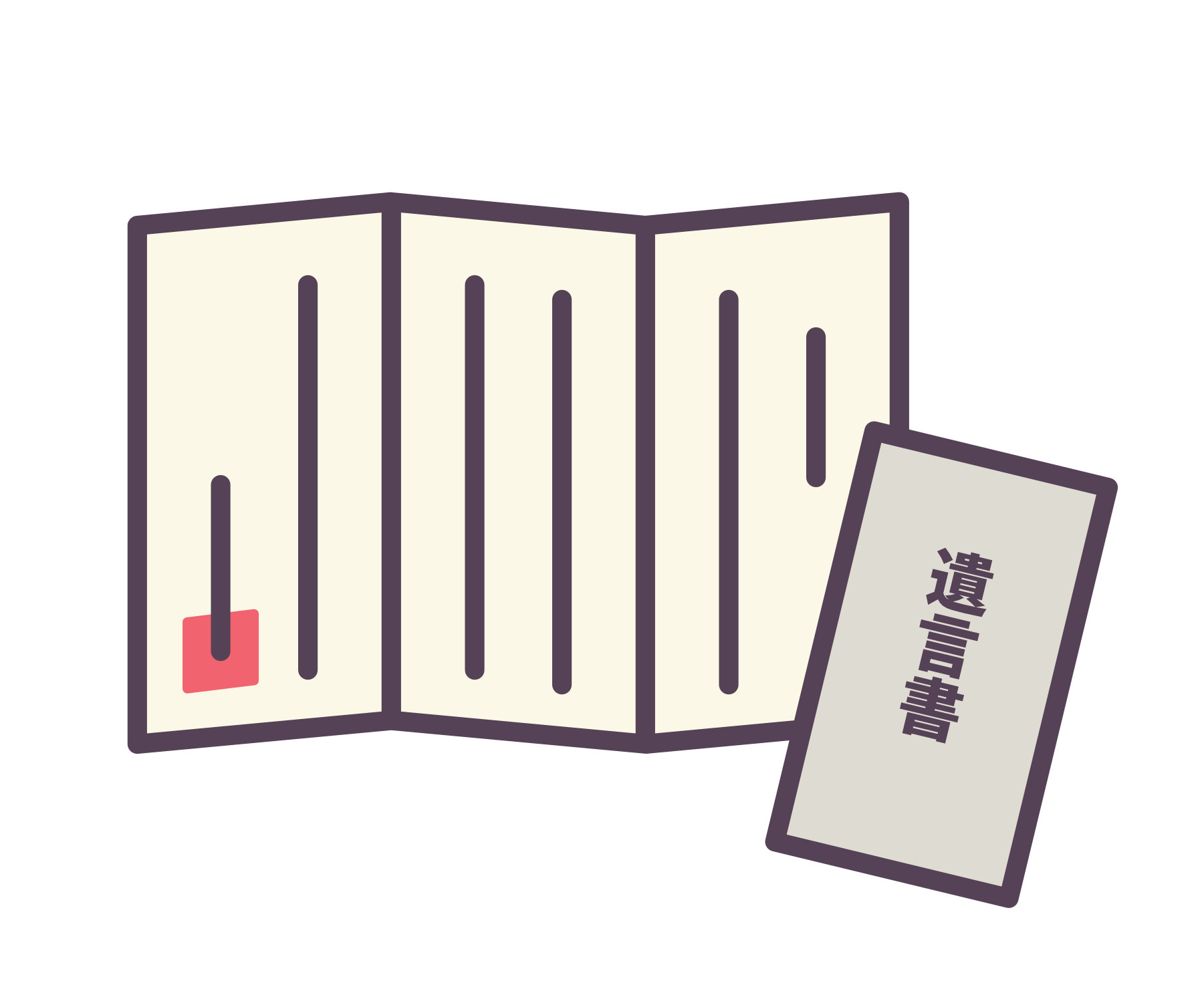
遺言書は遺言者の死亡後にしか効力が生じませんが、家族信託は契約締結時から効力が発生し、生前の財産管理にも活用できます。また遺言では一代限り(一次相続まで)しか指定できない承継先を、信託では契約内で二次相続、三次相続と次世代以降まで指定することも可能です。例えば「父→母→長男→孫」というように受益者を連続して定め、一族の資産を段階的に承継させる設計もできます。ただし、信託しなかった財産については従来どおり遺言書で指定する必要があります。農地など信託できない財産もあるため、状況に応じて遺言と家族信託を併用することも検討しましょう。
成年後見制度との違い
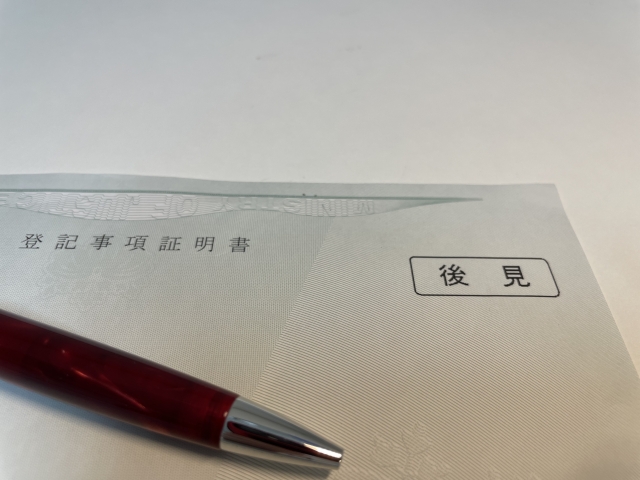
成年後見制度は、判断能力が低下した本人に代わり家庭裁判所が選任した後見人が財産管理や身上監護を行う制度です。すでに認知症などになった場合でも利用できますが、後見人の権限は本人の財産維持・管理に限られ、資産運用や生前贈与など積極的な財産活用はできません。例えば介護費用を捻出するため自宅を売却するにも、家庭裁判所の許可が必要で時間と手間がかかります。一方、家族信託は本人に判断能力があるうちに契約する必要がありますが、契約で定めた信託目的の範囲内であれば投資や不動産処分など柔軟な財産管理が可能で、家庭裁判所の関与なく迅速に対応できます。また成年後見制度には本人の身上監護(生活・医療・介護契約など)の機能がありますが、家族信託は財産管理に特化した制度のためその権限は含まれません。たとえば介護施設への入所契約や医療同意などは受託者でも代理できず、遠縁の親族や第三者が受託者の場合は法的に認められない可能性もあります。必要に応じて任意後見契約や法定後見制度の利用も検討しましょう。
家族信託の注意すべきポイント
遺留分とは、配偶者や子など特定の法定相続人に保障された最低限の取り分のことです(兄弟姉妹には遺留分はありません)。
家族信託で財産承継を決めておいても、他の相続人の遺留分を完全に無視することはできません。信託した財産も遺産の一部とみなされるため、信託によって特定の相続人に財産を集中させた場合、委託者死亡時に他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
実際、2018年の東京地裁判決では「遺留分を回避する目的で組まれた信託契約は無効」と判断されたケースもあります(後に和解)。家族信託を使えば遺留分対策になるという誤解は禁物です。
対策としては、信託設計の段階で遺留分に配慮することが重要です。他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で承継先を決めたり、遺留分権利者には別途生命保険金や遺贈を用意して手当てする工夫が考えられます。専門家によれば、家族信託だけでは遺留分対策として不十分で、生命保険の活用や生前贈与、家族会議での合意形成など他の手法と組み合わせて総合的に対策することが有効とされています。信託契約を結ぶ際は遺留分リスクについて専門家と十分に検討し、必要に応じて遺言書の併用や代償策を講じておきましょう。
家族信託の活用事例(ケーススタディ)
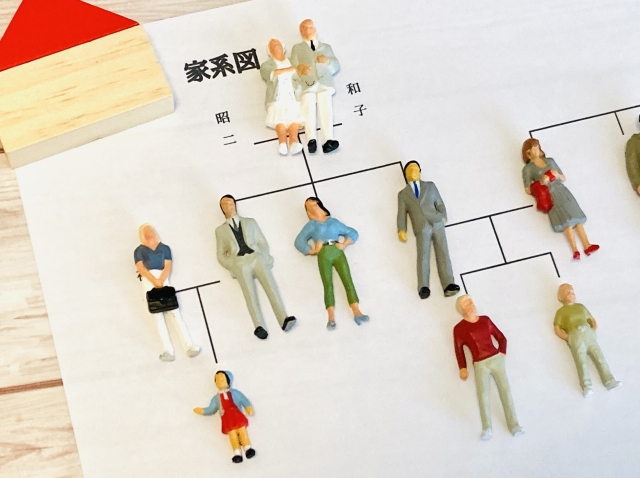
では、家族信託が実際にどのように活用されているのか、代表的なケースを見てみましょう。
- ケース1:親の認知症対策 – 70代の父親が、自身の判断能力低下に備えて自宅不動産と預貯金を長男に信託しました。父親を委託者兼受益者、長男を受託者とすることで、父親に認知症の兆しが出ても長男が代わりに銀行から年金を引き出し、医療・介護費用に充てることができました。口座凍結を防ぎ、成年後見人を立てずに家族が財産管理できるようにした例です。
- ケース2:不動産オーナーの資産承継 – 賃貸マンションを持つ母親が、将来的な資産承継と管理負担軽減のため娘に家族信託で不動産を託しました。母親を委託者・受益者、娘を受託者とした契約により、家賃収入の管理や建物維持を娘が担当しつつ、収益は母親が受け取ります。母親が亡くなった後は信託契約に従って当該不動産が娘に帰属するため、遺産分割の手続きを経ずスムーズに名義を引き継げました。
- ケース3:障がいのある子への備え – 高齢の父親が、自身の死後に残される障がいのある次男の生活費を確保するため、信頼できる長女を受託者として家族信託契約を締結しました。父親存命中の受益者は父親、死亡後は次男を二次受益者と定めています。これにより父親の死後、信託財産から生じる定期収入を次男が受け取れるしくみを構築しました。障がいのある子の生活保障に家族信託を活用した例です。
家族信託の落とし穴と注意点

便利な家族信託ですが、運用を誤ると思わぬトラブルを招く可能性もあります。事前に次のような点に注意しましょう。
- 受託者の負担と責任: 受託者には委託者から託された財産を信託目的どおりに管理・運用する義務があります。不動産管理や各種支払いなど業務は多岐にわたり、精神的・時間的負担が大きくなりがちです。受託者に権限が集中しすぎると他の家族との摩擦や、受託者自身が病気等で管理不能になるリスクもあります。必要に応じて共同受託者を立てるなど、負担軽減策を検討しましょう。
- 家族間の不信感・トラブル: 家族信託は家族の協力と信頼が前提ですが、情報共有やコミュニケーション不足によって他の家族が不信感を抱くケースがあります。例えば、受託者の長男が財産管理の内容を十分説明しなかったことで疑念が生じ、兄弟間の争いが訴訟に発展したケースもあります。契約前に家族全員で十分に話し合い、透明性を確保しておくことが重要です。
- 契約のタイミング: 家族信託を利用するには委託者本人に契約時点での判断能力が必要です。認知症が進行してからでは有効な信託契約を結べず、結局は成年後見制度を利用せざるを得なくなる場合があります。「元気なうち」に手続きを済ませておくことが何より大切です。親の判断能力に不安がある場合は、医師の診断書を取る、契約を公正証書で作成するといった対策で後日の無効主張リスクを下げられます。
- 税務上のリスク: 家族信託の組成・終了に伴い、相続税や所得税の扱いが変わる場合があります。例えば、信託不動産から生じた赤字は他の所得と相殺できないなど、一般の相続対策とは異なる税制上の制約があるため、事前に税理士等と検討し対策を講じておくことが望ましいでしょう。
信頼できる専門家に相談する際のポイント
・司法書士や弁護士など、家族信託の実績が豊富な人か
・信託実務に習熟しており、契約設計のミスを防げるか✅ 制度全体を理解しているか確認する
・家族信託のメリットだけでなく、デメリットやリスクも説明してくれるか
・法的・税務的なバランスに配慮したアドバイスがあるか✅ 他の終活手段も含めて提案できるか
・遺言・後見・生命保険などと組み合わせた提案が可能か
・遺留分への配慮や相続税対策まで検討してくれるか✅ 家族間の合意形成もサポートしてくれるか
・家族会議の進め方や調整役としてのサポートがあるか
・関係者全員が納得できる設計に導いてくれるか✅ トラブル防止を重視したプラン設計ができるか
・契約書の文言や財産の管理方法に明確なルールがあるか
・将来の誤解や揉め事を未然に防ぐ視点で設計されているか
終活の一環として家族信託を活用すれば、親の財産を守りながら円満な相続を迎える準備ができます。制度のメリットだけでなくデメリットや注意点も理解したうえで、信頼できる専門家と共に最適なプランを検討してみてください。家族信託は相続トラブルを未然に防ぐ有効な手段となります。

