通帳だけじゃ危険!いざという時にあわてない“銀行口座まるごと整理”ガイド
終活の一環として生前整理に取り組む際、特に優先して行いたいのが、預貯金を含む財産の整理です。
「預金の整理って、通帳やキャッシュカードを残しておけば十分では?」と考える方もいるかもしれません。しかし実際には、口座の名義人が亡くなった瞬間、その銀行口座は凍結されてしまいます。いくら通帳やキャッシュカードが手元にあっても、凍結された口座からお金を自由に引き出すことはできません。さらに、そのまま長期間放置してしまうと、口座維持手数料が発生する場合や、一定期間が過ぎて休眠口座となってしまう恐れもあります。
預貯金は、相続税の支払いに使われることもある大切な資産です。だからこそ、生前のうちから適切に整理し、いざというときに困らないよう備えておくことがとても重要です。今回は、銀行口座の預貯金も含めた財産全体の生前整理について、具体的な考え方をご紹介します。
通帳があってもお金は動かせない!? 相続で困らないための「口座凍結」

銀行口座の生前整理が必要とされる大きな理由は、通帳やキャッシュカードが手元に残っていたとしても、口座の名義人が亡くなるとその口座が自動的に凍結されるためです。
名義人の死亡後、遺族は速やかにその事実を金融機関へ報告する必要があります。これは、銀行にある預貯金が名義人の死によって相続財産と見なされるためであり、金融機関側は、遺産をめぐる権利トラブルを防ぐ目的で口座を一時的に停止(凍結)する対応を取ります。
口座が凍結されると、たとえ遺族が通帳やキャッシュカードを所持していたとしても、預貯金の引き出しや振り込みといった一切の操作が不可能になります。これによって、葬儀費用や急な生活費の支出に困ってしまうケースも少なくありません。
そのため、どうしても必要な支出に対応するために「仮払い制度」という制度も用意されています。これは、相続手続きが完了する前であっても、一定の範囲で預貯金の引き出しが可能となる制度です。ただしこの制度を利用するには、相続人全員の戸籍謄本や本人確認書類など、複数の書類提出が必要で、実際の手続きにはかなりの時間と労力がかかることを理解しておかなければなりません。
また、相続手続きが長引くと、凍結されたままの口座に対して口座維持手数料が発生する場合もあります。さらに、10年以上放置されてしまった場合には「休眠口座」となり、預金が公益目的で使われてしまう可能性もあります(※休眠預金等活用法による)。
このように、通帳やキャッシュカードが手元にあっても、死亡後の口座には厳しい制限がかかるため、生前の段階で口座情報をしっかり整理しておくことが非常に重要です。どの口座にどれだけの預貯金があるのか、どの銀行にどのような取引があるのかといった情報を明確にしておくことで、遺族や相続人が手続きに戸惑わず、スムーズに対応できるようになります。
万が一の時に慌てないためにも、口座の凍結リスクに備えた生前整理を、早めに始めておくことが大切です。
今からできる「銀行口座まるごと整理」
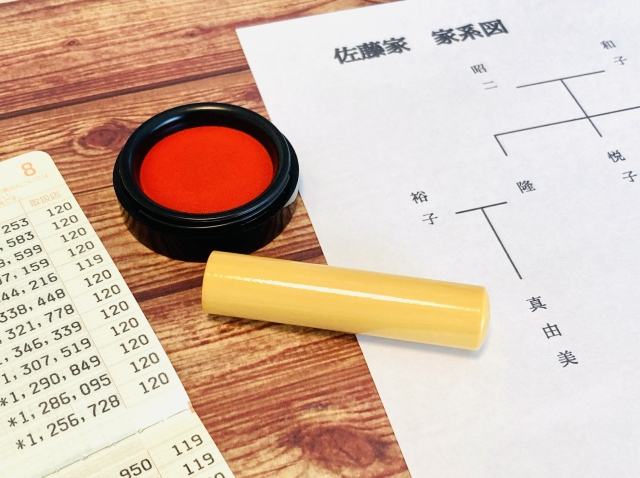
終活の一環として財産を見直す中で、銀行口座の整理はとても重要な作業です。遺族がスムーズに相続手続きを進めるためにも、生前にしっかりと状況を把握し、必要な情報をまとめておくことが欠かせません。
まず行いたいのが、自分が現在所有しているすべての銀行口座の状況確認です。中には、キャッシュカードはあるけれど通帳が見つからない口座や、その逆のケースもあるかもしれません。普段使っていない口座でも、意外に残高がある場合もあるため、1件ずつ丁寧に棚卸しを行いましょう。
状況を把握したら、いざというとき家族が困らないように、口座情報を整理して見やすくまとめておくことが大切です。
家族に共有すべき情報としては、以下のような内容があります。
- 銀行名・支店名・口座番号・暗証番号(ネット銀行の場合はログインID・パスワード)
- 通帳・キャッシュカード・印鑑などの保管場所
- 各口座で引き落とし設定されている支払い内容(公共料金・ローン・サブスクなど)
- 入金がある場合はその内容(年金・配当金など)
これらの情報は一覧表にまとめておくと非常に便利です。まとめた資料は、遺言書やエンディングノートと一緒に保管しておけば、遺族が必要なときにすぐ確認できます。
預貯金の整理は、自分の資産を明確にするだけでなく、家族の負担を減らす思いやりでもあります。まだ元気なうちに少しずつ取り組んでおくことが、安心して日々を過ごすための備えになるでしょう。
預貯金以外の財産が多い場合は「財産目録」を活用しよう
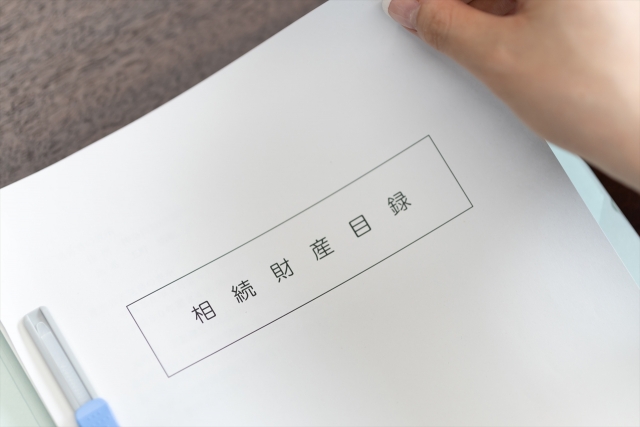
預貯金だけでなく、複数の金融資産を保有している方は、生前のうちに財産目録を作成しておくことが非常に有効です。預貯金とその他の財産情報を一括で管理できるようにしておくことで、いざというときに家族が困ることなく手続きを進められます。
財産目録とは
自分が保有しているすべての財産と負債を一覧表としてまとめたものです。預金残高だけでなく、不動産の所有状況、株式・投資信託などの有価証券、さらには住宅ローンや各種ローンといった負債も記載し、全体像を明確にすることが目的です。
もしものことがあった際、遺族は相続手続きを始める必要があります。遺言書が残されていない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことになりますが、その前提として、すべての相続財産を把握しておく必要があります。財産目録が用意されていないと、まず財産の洗い出しから始めなければならず、想像以上に時間と手間がかかってしまいます。
特に注意が必要なのは、相続税の申告・納税には期限があるという点です。相続の開始から10カ月以内に完了しなければ、延滞税などのペナルティが発生する可能性があります。そのため、財産目録を整えておくことで、手続きを滞りなく進めることができるのです。
なお、財産目録の作成は法律上の義務ではありませんが、生前に財産を可視化し、整理しておくことには家計管理の面でも大きなメリットがあります。老後の生活設計を立てるうえでも、自分の資産状況を正確に把握しておくことは安心材料のひとつです。
財産は時間とともに増減するものですから、一度作って終わりではなく、定期的に見直して最新の状態に更新することが重要です。こうした習慣が、ご自身と家族の両方にとって、将来の安心につながっていくでしょう。
財産目録に含めておきたい資産と作成時の注意点
財産目録の作成には法的な書式の決まりこそありませんが、記載漏れがあると、相続税の申告漏れやトラブルの原因になる可能性があるため、内容には細心の注意が必要です。
作成する際は、財産の全体像をもれなく把握することを意識し、主な資産の種類をリストアップしておくことが大切です。
<財産目録に含めたい主な資産の例>
- 預貯金:普通預金、定期預金、積立預金など口座種別ごとに整理
- 有価証券:株式、投資信託、国債、社債などの金融商品
- 不動産:持ち家、別荘、土地など所有している不動産全般
- 保険:生命保険や個人年金保険など、資産価値のある保険商品
- その他の資産:絵画、骨董品、美術品など、資産性の高い動産類
- 負債:住宅ローン、マイカーローン、教育ローンなど、現時点の残高も記録
このように、財産だけでなく負債もあわせて記載しておくことで、相続に必要な情報が一目で分かる一覧表となります。
<財産目録作成時のポイント>
-
- 財産目録には「作成日」と「更新日」を明記する
- 預金や証券は、金融機関名・支店名・口座番号・名義人・連絡先を記載する
- 不動産は登記簿情報を、不動産以外の資産は種類ごとの必要情報を明記する
- 負債は記載時点での残高を明確に記録する
- 内容に迷った場合は、銀行・税理士・ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談する
また、家庭裁判所のホームページでは、遺産目録のひな形(テンプレート)や記載例が公開されており、初めて作成する方でも参考にしながら進めることができます。
大切なのは、将来の相続人が情報を探し回ることなく、一目で内容が把握できるように整理しておくこと。正確で分かりやすい財産目録は、家族の負担を大きく軽減する心強い備えになります。
銀行口座を生前に整理するときの落とし穴と安全対策

これまでご紹介してきたように、銀行口座を含む財産の生前整理は、いざという時に家族が困らないようにするための大切な備えです。ここでは、特に押さえておきたい3つのポイントについてまとめました。
使っていない銀行口座は解約して集約を検討する
通帳やキャッシュカードを見直すと、かつての職場の給与振込用口座や、キャンペーン目的で開設したまま使っていない口座などが見つかることがあります。今後も使わない口座については解約し、預貯金を1〜2口座にまとめておくと管理がしやすくなります。
ただし、預金保険制度の上限である1,000万円を超える資産を預けている場合は、金融機関を分散することでリスクヘッジになります。また、複数口座のほうがライフスタイルに合っているという方は、無理に集約する必要はありません。整理の際は、現時点で使用していない口座を優先的に見直すことを意識しましょう。
通帳は磁気不良を防いで正しく保管する
通帳に記録された預金残高や取引履歴は、相続財産の内容を把握する上で重要な情報です。ところが、磁気不良が発生するとATMで記帳できず、窓口での再発行が必要になってしまいます。いざというときにすぐ使えるよう、磁気防止ケースに入れて保管しておくことが安心です。
「今はまだ伝えたくない」という人も、準備だけはしておく
財産情報を家族にすべて開示することに抵抗を感じる方も少なくありません。特に、相続人が複数いる場合や、資産が多い方は慎重になるのも当然です。「今はまだ言いたくないけれど、死後に備えておきたい」という場合は、以下の方法を検討してみてください。
- Excelなどで一覧を作成し、パスワードを設定して保管
→ パスワードは信頼できる家族に伝えておくか、死後に目に付きやすい場所に置く工夫を - 法務局の遺言書保管制度を利用して財産目録も一緒に預ける
→ 自筆証書遺言とあわせて財産目録を作成し、署名・押印などの要件に注意 - 銀行の貸金庫や有料の預かりサービスを利用する
→ エンディングノートや財産情報を安全に保管でき、金融機関のサポートも受けられる
資産が多くて自分では整理しきれないという方や、情報を安全に管理しておきたい方は、専門家や金融機関への相談も検討すると良いでしょう。信頼できるサービスを活用することで、大切な情報を確実に守ることができます。

