生前戒名ってやるべき?お布施の相場とメリットをざっくりチェック
戒名(浄土真宗では「法名」)は、故人が仏門に入った証として授かる名前であり、一般的には亡くなった後に僧侶から授与されます。これは、現世での名前を手放し、仏弟子としての新たな名を持つことで、浄土への旅立ちを表す意味があります。
ところが、近年は「終活」という言葉が広く知られるようになり、人生の最終段階を前向きに整えておきたいという考えが広がる中で、「生きているうちに戒名を授かりたい」と希望する人も増えてきました。では、そもそも生前に戒名をもらうことにはどのような意味や価値があるのでしょうか。また、お布施の相場や気をつけるべきポイントは何か。ここでは、生前戒名の基本から実際に授かる際の注意点までを詳しくご紹介します。
生前戒名とは?その意味と戒名との違いについて

生前戒名とは、通常は死後に授かる戒名(※浄土真宗では法名と呼ばれます)を、生きているうちに自らの意思で授かることを指します。一般的な戒名が故人に与えられるものであるのに対し、生前戒名は本人が仏門に入ることを自ら望み、僧侶に依頼して与えられるものです。
戒名は、本来、亡くなったあとに仏教徒としての新たな名前を授かるという考え方に基づいています。一方、生前戒名も仏弟子としての名前である点は同じですが、「いつ授かるか」というタイミングの違いがあるだけで、仏門に入るという意味では本質的な違いはありません。
ただし、生前戒名には一つ大きな特徴があります。それは、本人の希望や価値観がそのまま反映される点です。生きているうちに僧侶と相談しながら、納得のいく内容で授かることができるため、名前の文字や意味に自身の想いを込めることも可能です。
対して、死後に授かる戒名は、すでに本人が亡くなっているため、家族や親族が故人に代わって僧侶と相談し、戒名を決める流れになります。そのため、本人の考えが反映されることは難しく、宗派の慣例や家族の意向が中心になります。
つまり、生前戒名と通常の戒名の違いは、授かる時期だけでなく、そこに本人の意思が反映されるかどうかという点にも大きな違いがあると言えるのです。
死後ではなく生前に戒名を授かる意味とその必要性について
本来、戒名は死後に授かるものとされてきました。ところが、近年では生きているうちに戒名を授かる「生前戒名」を選ぶ人が少しずつ増えています。しかし、中には「死を連想させる」「縁起が悪い」と感じる人もいるかもしれません。
日本では、死にまつわる迷信や風習が今も色濃く残っています。たとえば、友引の日に葬儀を行うと「友を引く」とされ、忌避されてきました。また、葬儀後に塩で身を清めるという習慣も、不浄を遠ざけるという考え方に基づいています。こうした文化背景があるために、生前に戒名を授かることに抵抗を感じる人がいるのも自然なことかもしれません。
しかし、生前戒名は単なる迷信や風習とは異なり、もっと個人的で内面的な意味を持つ行為です。生きているうちに戒名を授かるということは、避けられない「死」という現実に向き合い、今をどう生きるかを考えるきっかけにもなります。自ら仏門に入るという覚悟を持ち、人生の締めくくりを自分で整えるという行為は、決して後ろ向きではなく、むしろ前向きな人生の選択とも言えるでしょう。
また、生前戒名には実務的な利点もあります。通常、戒名は遺族が葬儀の場で僧侶に依頼し、授かるものですが、生前戒名ではその一連の手続きを本人が事前に済ませるため、家族の負担を大きく軽減できます。葬儀の場で突然決めなければならないというプレッシャーからも解放され、残された人にとっても精神的な助けとなるでしょう。
加えて、費用の面でも生前戒名はメリットがあります。戒名にかかるお布施は、死後に依頼するよりも生前に授かるほうが安くなる傾向があり、経済的な負担も抑えられる可能性があります。これは、葬儀の中での儀式的な要素が含まれない分、僧侶の手間や時間も少なく済むためです。
このように、生前戒名には精神的にも実務的にも多くの利点があり、死後に授かる戒名とは異なる価値があります。迷信にとらわれるのではなく、自らの人生と向き合い、残された時間をどう生きるかを見つめ直す機会として、生前戒名は大いに意義のある選択だと言えるでしょう。
- 生前戒名は死後に授かる戒名よりもお布施が安く済む傾向がある
- お布施が安い理由は、葬儀対応などの寺院側の負担が少ないため
- 生前に戒名を授かることで、寺院との関係構築や将来的な檀家入りの可能性がある
- 自分の希望を戒名に反映させることができる
- 寺院との打ち合わせを通じて、納得のいく戒名を選ぶことができる
- 生前のうちに準備を整えることで、家族への負担を軽減できる
戒名お布施の相場とは?
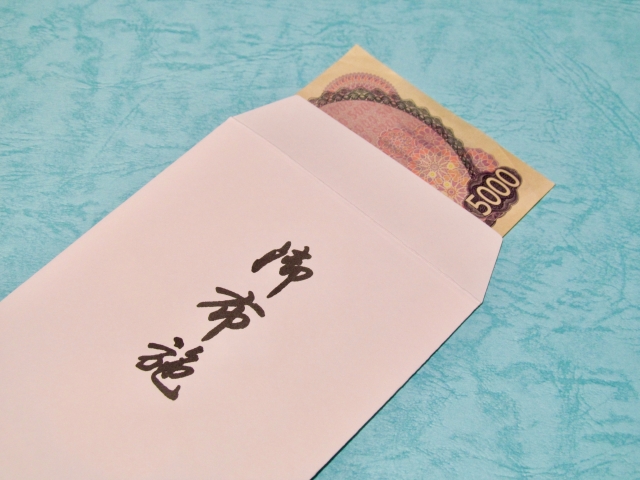
| 宗派 | 死後戒名のお布施相場 | 生前戒名のお布施相場 |
|---|---|---|
| 浄土真宗(法名) | 約20万円 | 約10万円 |
| 浄土宗 | 30〜40万円 | 15〜20万円 |
| 曹洞宗 | 30万円以上 | 15万円以上 |
| 真言宗 | 30〜50万円 | 15〜25万円 |
| 日蓮宗 | 30〜50万円 | 15〜25万円 |
生前戒名を授かる際の注意点と避けたいトラブルについて

生前戒名を授かることには多くのメリットがありますが、実際に行う際には注意すべき点も少なくありません。特に「どこのお寺に依頼するか」という点を誤ると、後に思わぬトラブルに発展する可能性があります。
生前戒名を授かる際には、まず依頼先の寺院が自宅の菩提寺であることが必須です。菩提寺とは、先祖代々のお墓を管理してもらっているお寺のことを指し、葬儀や法要の際にも依頼をしているような、深い宗教的つながりのある寺院です。
このような関係にある家を「檀家」と呼びます。檀家は、宗教的な行事や儀礼について、その菩提寺の宗旨・宗派に従うことを前提としています。そして、僧侶のお勤めや管理に対しては「お布施」という形で支援を行うことで、寺院の運営を支える役割も果たしています。
このため、檀家としての関係がある家庭は、必ず生前戒名は菩提寺に依頼しなければならないというルールがあります。もし、無関係な寺院に依頼して生前戒名を授かってしまうと、後々、菩提寺との関係に亀裂が生じる可能性があります。
たとえば、納骨の際に「その戒名では受け入れられない」として、納骨を断られてしまうケースも実際に起こり得ます。これは、宗派の考え方や、戒名の授与が正式なものとして認められていない場合に起こるトラブルです。
たとえ納骨自体は拒否されなかったとしても、結果的に菩提寺側から「改めて戒名を授かるように」と求められるケースもあります。その場合、二重にお布施が必要となり、経済的にも無駄な出費が増えてしまうことになります。
さらに、このようなやりとりが原因で、菩提寺との信頼関係が損なわれてしまうと、以後の葬儀や法要などに支障が出ることもあるでしょう。菩提寺との関係は、一度こじれると修復が難しく、親族全体にも影響が及ぶ可能性があります。
こうしたトラブルを避けるためにも、生前戒名を希望する場合は、必ず事前に菩提寺へ相談し、了承を得たうえで進めることが大切です。誤った判断をしないためにも、日頃から寺院との関係を大切にし、意思のすれ違いが生まれないよう心がけることが求められます。

